- 40周年
- 地域文化ナビ
2020年04月06日
- [近畿]
サントリー文化財団40周年記念フォーラム
「文化がひらく地域の未来
~今、私たちにできること」
2020年3月8日(日)、NHK大阪ホールにて、標記のフォーラムを実施しました。 ただし、コロナウィルス感染拡大防止のため公開は中止に。
ただし、コロナウィルス感染拡大防止のため公開は中止に。
1200名近くの参加申し込みをいただいていたのに本当に残念です。
お申込みいただきました皆様には、誠に申し訳ございませんでした。
そして、当日は、非公開でフォーラムを実施したのであります。
 NHKさんによる収録が行われましたので、そのスタッフの方々と、
NHKさんによる収録が行われましたので、そのスタッフの方々と、
当財団関係者のみの、ガランとした客席です。
第1部は、政策研究大学院大学教授の飯尾潤先生による
「地域文化 続けるヒント」と題したご講演です。 飯尾先生には、当財団が開催した「地域文化の未来を考える研究会」
飯尾先生には、当財団が開催した「地域文化の未来を考える研究会」
の代表として、地域文化活動を長く続ける知恵をまとめた冊子
『続けるヒント』(リンク先で全文が閲覧できます。)の編集にご尽力をいただきました。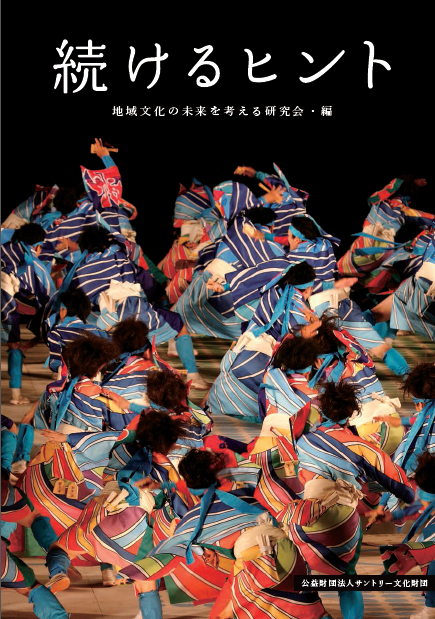
全国各地の多彩でユニークで楽しい地域文化活動が、
続けることが困難になりつつある現状を分析し、
それに対応するためのヒントについてお話をいただきました。
それは、本当に大切なことはなにかを考える"活動の棚おろし"を行い、
活動団体の中と外にある"仕切りをはずす"こと。
仲間内や行政・周辺団体、地域の人々と"ゆるやかにつながり"ながら、
観客動員数や評価を気にして"まわりに流されない"ことです。
文化活動は楽しいからとか、どうしてもやりたいという気持ちが
何よりも大切と強調されました。
地域の良さはかけがえがなく、その一つが地域文化。
まだ参加したことがない人は、ちょっと勇気を出してお手伝いをしてみたら、
人生はもっと楽しくなるし、地元の地域はもっと豊かになる。
みんなで楽しんでください、とエールを送られました。
続く第二部はパネルディスカッションです。
地域文化活動の担い手の方々にパネリストとしてお集まりいただきました。
山岡奈穂子さんは、高知生まれの高知育ち。高知市役所に入庁してすぐに、
「高知市役所踊り子隊」に参加。
踊り子隊は、70年近い歴史があるよさこい祭りに第1回から参加し、
正調よさこい鳴子踊りを披露している団体です。
山岡さんは、「正調よさこい鳴子踊り普及振興会」の副会長も務めています。
東京で暮らしている二人の娘さんたちも幼いころから祭りに参加していて、
祭りの時期には必ず帰ってくる。
祭りは、帰ってくることのできる心のふるさとだと感じているそうです。
1999年に山岡さんが立ち上げを担当した「よさこい全国大会」をきっかけに、
今では、県外から多くの人たちが本場高知のよさこい祭りに参加しています。
その人たちが祭りを盛り上げてくれているばかりか、演舞場や競演場の運営の
お手伝いもしてくれていることが非常に嬉しく、心強く感じているそうです。
地域文化活動は、楽しくなければ続かない。
でも、やってみないと楽しさは分からない。
だから、若い世代の人たちには、「まぁ、いっぺん、やってみぃやぁ」
と伝えたいと述べられました。
小岩秀太郎さんは、公益社団法人全日本郷土芸能協会の理事であり、
ご自分のふるさと岩手県の郷土芸能「鹿(しし)踊」の継承者です。
故郷を襲った東日本大震災を契機に、多国籍・多世代・多分野の人々を
巻き込む「東京鹿踊」と、東北の地域文化の魅力を発信する
「縦糸横糸合同会社」を設立しました。
小学生のときに授業で「鹿踊」を習ったときは嫌々だったのですが、
上手だと褒められた一言が40歳過ぎまで続けるきっかけになったとのこと。
小岩さんは生まれ故郷をあまり好きではなかったそうです。
でも、一度東京に出たことでふるさとを見つめなおし、
全国の郷土芸能の担い手たちと知り合い、仲間になることで、
お互いの芸能を認めあい、誇りが生まれたと話されました。
そして、震災の年のお盆に、死者を供養するという
「鹿踊」本来の役割を実感。
演者とそれを支える裏方、観客がひとつの場に集い、関わりあい、
思いをひとつにつなぐことをできる郷土芸能は、
コミュニティの核になりえると確信したそうです。
そんな郷土芸能の魅力を発信し、人々と郷土芸能そのものを元気にしたいと
考えて始めたのが、「東京鹿踊」と「縦糸横糸合同会社」なのです。
ニコラ・リバレさんはフランスはのブルターニュ州出身。
大学生のときに、パリでたまたま知り合った日本人の実家にホームステイ。
富山県に何度も通ううちに、福野町(現・南砺市)で行われている
ワールドミュージックの祭典「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」
に出会いました。
「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」は、2002年にサントリー地域文化賞を
受賞されています。

一流の音楽と、この音楽イベントで地域を盛り上げようという熱意に燃える
地元のボランティア・スタッフたちに惹かれてお手伝いを申し出て、
2001年にイベント会場である福野文化創造センターに採用され日本に移住。
現在は、同センターと「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」の
総合プロデューサーとして活躍されています。
地元の文化と全く関係のないこのフェスティバル。
まず、当初、プロモーター任せだった企画をすべてを
地元のボランティア・スタッフで行うようにしました。
アーティストによるワークショップを行った結果、地域住民自ら、
海外の音楽を演奏して楽しむようになりました。
30年間、様々な変革や新しいプロジェクトにチャレンジしていったおかげで、
自分たちのイベントなんだという思いが地域に浸透し、
根付いていったそうです。
ニコラさんの最後のメッセージは、活動を通じて、誰もが対等に、
自由に意見を言い合える仲間ができる。
普段はなかなか会えないような人とも出会える。
音楽には関心がなくても、何かのきっかけだと考えて参加して、
自分の持っている力を発揮することができれば、
人生は30倍くらい楽しくなってくる。
活動に参加しなければ、自分にとっても地域にとっても損だから、
若い人たちにもどんどん参加してほしいというものでした。
宮沢和史さんはミュージシャンであり、
「くるちの杜100年プロジェクトin読谷」の名誉会長です。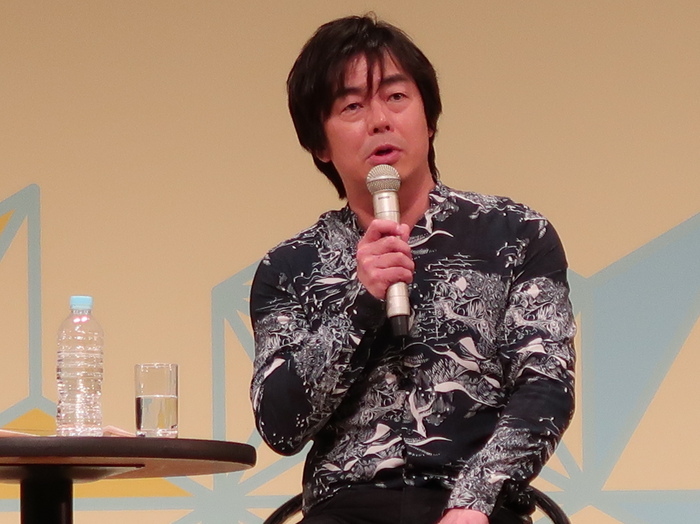
30年ほど前に沖縄民謡に魅了されて沖縄に通い、
「島唄」が大ヒットした宮沢さん。
ある日、「島唄」でも使われている沖縄独特の楽器、
三線(さんしん)の棹の部分の材料である琉球黒檀、くるちの樹の多くが
沖縄戦で焼失し、今では輸入に頼っているという話を聞きました。
三線は、沖縄の芸能には欠かせない楽器。
「ないんだったら、僕が植えよう」と考えたそうです。
ところが、くるちの樹は成長が遅く、棹の材料となる芯の部分が
十分な大きさになるには、100年から300年はかかるということを知りました。
当初は一人でもやろうと思っていた活動ですが、
これは仲間を集めないと続けられない。
宮沢さんの呼びかけに応えて、同じ思いを持つ人たちの協力の輪が広がり、
2012年、読谷村の全面協力も得て、プロジェクトがスタートしました。
100年というタームは気が遠くなるような時間。
少しひるんだこともあるそうですが、東日本大震災をきっかけに、
いつかやろうと思っていたことは、すぐやろう。
始めなければ始まらないと思い立ったそうです。
今では、読谷村以外の地域にもプロジェクトが広がり、
もし、病害虫の被害でひとつの地域のくるちが駄目になっても、
ほかの地域のくるちが元気に育つような体制も整い始めています。
毎月、草刈りのために沖縄にわたり、どんどん成長するくるちを見るのが
楽しみで仕方がないという宮沢さん。
このくるちが三線にできるくらいに大きくなるということは、
その間、沖縄に戦争がなかったということ。
自分が決して耳にすることができない三線の音色を思い浮かべ、
ずっと平和が続くことを祈りながら、
ひ孫の世代に沖縄産の三線を手渡せるように、
これからもくるちを植え続けたいと語られました。
すでにHPなどでお知らせしておりますように、
このフォーラムは2020年5月9日(土)午後2時から、
NHKのEテレ「TVシンポジウム」で1時間にわたって放送予定です。
この番組をご覧になって、少しでも多くの方が、地域文化の魅力に触れ、
自分も参加してみようかなと思ってくださることを祈っております。

